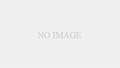●語り:向井秀徳(ミュージシャン:ナンバーガール/ZAZEN BOYS)
「平成」はどんな時代だったのか。
ここでは歌舞伎町に絞って振り返ろう。数多くの写真家が歌舞伎町に魅了されてきたが、20年以上撮影を続けているのは韓国人カメラマンのヤン・スンウーだけだ。写真界の直木賞といわれる「土門拳賞」を、外国人として初めて受賞。とにかく被写体との距離が近い。ヤクザだろうが、喧嘩の現場だろうが、必ず声を掛けて撮影し見る者を圧倒する。しかし、被写体の宝庫だった歌舞伎町に、異変が起きているという。平成の最後に、ヤンと街を歩いた。
―“人間の匂い”を感じづらくなった
ネオンが眩しい風俗店。呼び込みの男たち。一見すると、歌舞伎町は以前とあまり変わっていないようだ。しかし、路上で目立つのは酔客ではなく、外国人観光客や親子連れ。どこにでもいたヤクザも見当たらない。「2004年の浄化作戦以降、ヤクザを路上で撮影できる機会は減っていきました」ヤンに言われて目線を上げると、防犯カメラが至る所に設置されていた。明け方まで歩いても、ヤンが撮影していた異常ともいえる熱気は感じられない。平成という時代は、歌舞伎町を他の歓楽街と変わらないクリーンでクールな街に変えてしまったのか。
―今も片隅に残る“人の熱”
「一晩中歩いても、シャッターを1枚も切れない時がある」というヤン。しかし粘り強く歩くと、歌舞伎町らしい光景がまだ少し残っている。この夜偶然出会ったのは、キャバレーの支配人・吉田康博さん。歌舞伎町で60年以上働き続けている。「平成はネオン街にとって衰退の時代だった」ヤンは“狂ったように”キャバレーでシャッターを切った。
―歌舞伎町を去った“詩人ホームレス”
かつては、深夜でも人がごった返していた旧コマ劇前の広場。いまは、人がまばらだ。「東京五輪に向けた再開発などで、ホームレスたちは、徐々にいなくなっていきました」この広場で暮らしていた一人が、通称・ゴン太。複雑な家庭で生まれ育ち、二十歳の時に家を飛び出し、歌舞伎町でホームレス生活を送っていた。しかし重度の糖尿病が見つかり、数年前から川崎で生活保護を受けている。ゴン太はホームレス時代から詩を書き、ヤンは写真を撮る。2人は、それを贈り合う“友達”だ。平成の最後に2人は、思い出の歌舞伎町を歩いた。ファストフードの店長が、余り物をくれたこと。酔っ払いのサラリーマンが、缶コーヒーを置いて行ったこと。思い出すのは、多様な人々が集まる歌舞伎町で、時に触れた“人の優しさ”だった。「ネオンが僕の寂しさを、紛らわせてくれたのかなぁ」ゴン太を受け入れた歌舞伎町の姿は、もう無い。街を去っていくゴン太を尻目に、ヤンはこれからも歌舞伎町を撮影し続けるという。「未来と現在と過去は、まだまだ少し残っています。そこを僕は掘り下げて、令和の時代になっても、死ぬまで撮り続けます」“狂気の”韓国人カメラマンが残した歌舞伎町の写真は、私たちの心に「平成という時代」をストレートに投げかけてくる。
あなたが見た時代や歌舞伎町は、きっと彼の写真の中にある。
#Tokyo #Yakuza #歌舞伎町