スイス政府の非正規ダウンロードも合法という報告について知り大変興味深く思いました。
将来は著作権ビジネス自体が成立しなくなると聞いて、スイス政府の決断が将来に適応したものであるのなら
著作権の概念そのものが変わるというか、かなり薄くなるのは当然だと思いました。
一方で、作家たちが書籍の電子化を代行するスキャン業者を訴えましたが、そのさい「作家や漫画家が職業として成り立たなくなる」と言っておりました。
ミュージシャンにしろ作家にしろ、それ以外の創作に関する職業にしろ、著作権が創作を支えてきたことは間違いないと思いましたが、それが失われた未来は、あるユニークな発想を持った個人が作る個性的な作品ではなく、市場調査に基づいた消費者に迎合したものばかりになるのではないでしょうか?
そんな極端なことになる前に自浄作用のようなものが働くのではとも思いますが、
”創作”に関する新たなビジネスモデル、或いはそのあり方はどのようなものになると思いますか?
可能な限り具体的に(例や根拠なども交え)教えていただければと思います。
スイス政府の非正規ダウンロードも合法という報告について知り大変興味深く思いました。 将来は著R…



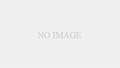
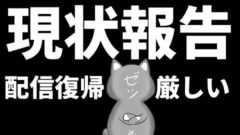


うーむ、何で俺に聞くんだか、サッパリ解らん
まあ確かに、この10年位で、本来、創作や創造というクリエイティブな企画は減り、やたら企業側も
《天才はいらねえ、社会を分析し、対応し、手軽にいけ》
みたいな風潮が強まったし、実際そうなっている
まあ今や、あの、創作の固まりであった[ドラクエ]すら、その理念が曲がった
マンガや音楽も、その芸術性や理念は二の次、今や《賞味期限1週間》の代物だ
まあ、これからの10年は、あらゆる分野での《二極化》は、ある意味避けられないだろう
つまり、もはや
[大衆に働き掛ける]という《目的ありきにする事自体》が
その賞味期限を、さらに短くしてしまう要因になると感じる
つまり創作の《自転車操業化》だな
当然賞味期限が短いから、質より量での発想になる
ま、つまり著作権が弱体化していくと
その創作活動は、直接間接問わず《企業のお抱え》みたいになる
個人では無く、あくまでも《企業としてのプロデュース》だな
ま、漫画家なんかみても解るが、有名な漫画家は、その大半はアシスタントが描く
だが、その漫画家が《全て描いている》様な印象がある
しかし実際は《アトリエ〇〇》みたいなもんだからな
ま、企業の中で、社会分析や傾向を別部門が調査し、それを《企画》し、最終的に《形》にし、売り込む
ありとあらゆる《才能》は、この一連に組み込まれてしまうだろう
これが10年は続く
まあ、今はその最中かも知れん
だが必ず、それでは《収まり切らない才能》が、いつの時代も現れるもんだ
この世の中のシステムを熟知、利用する
ある意味《現代版フォーライフレコード》や《現代版無名塾》が現れる
それを信念を持って《隠れながら準備出来るか》だな